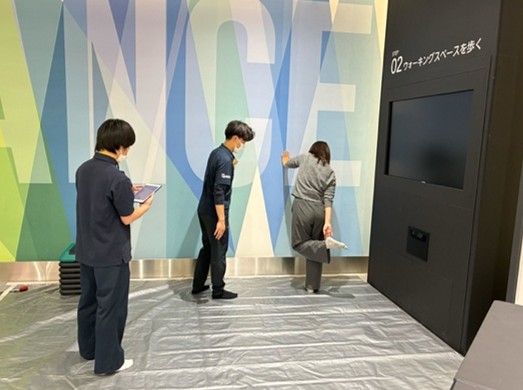-
サッカー界全体と地域が協力して7つの障害者サッカーをアシスト!
-
- レポート
これまでスポーツの分野においては「障害者」と「健常者」は分けて捉えられ、各競技を管轄する団体は大半の競技が「障害者団体」と「健常者団体※1」が個別に存在している状況です。
行政でも、かつては障害者スポーツの所管は「厚生労働省」でしたが、現在はスポーツ庁に業務が移管され、例えばトップアスリートの強化では「オリパラ一体化」の方針で取組が進んでおり、自治体レベルでも障害者スポーツの管轄を福祉部局ではなくスポーツ部局に一元化する動きが一定程度認められます。しかし、活動ベースでは、まだまだ「障害者」と「健常者」で個別に実施されているのが現状です。
このような課題に対応して水泳界では2013年10月に3つの障害種の水泳団体を構成員に日本障がい者水泳協会を設立し、2014年2月に日本水泳連盟に加盟。2016年4月には日本サッカー協会の傘下団体として7つの障害種のサッカー団体を構成員に日本障がい者サッカー連盟を設立。また、2018年4月には日本バスケットボール協会の傘下団体として4つの障害種のバスケットボール団体を構成員に日本障がい者バスケットボール連盟が誕生しました。
このような障害の有無や障害の種類に関わらない連携が活発になり、課題の解決等が図れることが望まれます。
今回はサッカー界の取組についてレポートしていきます。
※1 現在、障害種に応じたルール変更・設定を行った競技ごとに個別に競技団体が組織されることが一般的であり、結果として、一般の競技団体が健常者を対象とした競技団体となっている状況にある。